経営指針物語 5
"第5話 バス路線は廃止になった"
横木 正幸
そして三番目の第一は、「商品・技術第一主義」=科学性だという。これは無意識で今までやってきたことだ。よい商品絽を、よい技術をよい技術を提供する事は当たり前の事だ。これは大丈夫だと思った。ところが、今までの哲学?の世界とは全く違った展開になった。
突然、決算書を分析するのだという。今まで決算書は「売上」と「利益」の欄しか見たことがないのに、さあ、困った。しかし、数学の理解なくしてはあり得ないという。全くその通りだ。
だがしかし、…はじめて聞く言葉ばかりだ。流動資産、流動負債、固定資産、剰余金、営業利益、自己資本比率、売上原価に限界利益ときた。言葉自体が分からない。こんな事がわが社の中で行われていたのかと驚く。
そこで渡されたのが魔法の「10年シート」という用紙。いくつかの前提条件を設定する事により、10年先を見透すのだという。
そんな事が出来るのだろうか?来年の話をしただけでも鬼が笑うというのに。半信半疑で取り組む。とりあえず、損益の世界から取り組んだ。
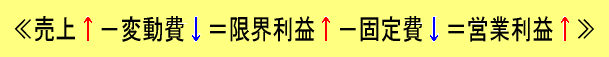
上の式の矢印をどう動かすかを「数値計画」というのだそうだ。そうか、数字を動かす事を「計画をたてる」ということなのかと分かってくる。
電卓をたたき続けること100日間。何と10年先がしっかりと見えてくるではないか。何度繰り返してもツジツマの合わなかった数字が、ピッタリと合ってくる。「数字はウソをつかない」という言葉がだんだん理解出来るようになってくる。
話は変わるが、ここのところ全く先の見えない時代になっている。政府を先頭に構造改革に取り組んでいる時代である。なぜ、いま構造改革なのか。
経済の変化は大きく二つに分けられるという。
前へ 次へ
|